
先日、三浦小太郎さんが、かつて自分の書いた「無法松の影」という本をとりあげて、えらくほめてくださっていたんですが、それを受ける形で、今日はその素材になった「無法松の一生」の話をしろ、ということなので、少しお話しさせていただきます。
というのも、たまたまいま、ご当地札幌で、映画版の「無法松の一生」が上映されているんですね。札幌駅の上のシネコン、札幌シネマフロンティアで、毎日朝10時からの一回だけということですが、先週17日から今月末30日まで期間限定でやっている。これは何かのお引き合わせかもしれない、ということで、その上映を勝手に後押し、宣伝するような意味あいも含めて、そしてまた「無法松の一生」を知らない、あるいはちゃんと映画でも見たことがない、という人たち、おそらくもう若い人はもちろん、50代くらいから下でもご存知ない方がほとんどになってしまっているでしょうが、そういう人たちにも、あ、ちょっと興味ある、おもしろそうだ、という感想を持っていただいて、映画館に足を運んでいただけたら、という思惑もあります。
といいますのも、この「無法松の一生」というおはなしは、ある世代までのわれわれ日本人の一般教養のひとつと言っていいような「おはなし」だったと思うからです。こういう一般教養的なおはなしというのは、無法松に限らず、たくさんありました。忠臣蔵もそうでしたし、清水次郎長伝、王将坂田三吉の話から渋谷のハチ公の話、さらには乃木将軍や爆弾三勇士といった教科書に載せられたような近代の戦争にまつわる英雄譚なども含めて、特にそれが学校で教わるようなものでなくても、あるいは教わるような形そのままでなくても、なぜかいつの間にか耳にしたり眼にしたりで、何となくどういうおはなしか程度は知っていた、そしてそれらを介して人生、生きてゆく上で必要な教訓や価値観、大事なことを教わるようになっていた、そんなおはなしの一群です。
そのようなおはなしを、まあ、民俗学の視点から、それがどのようにもともとのおはなしから映画や芝居その他さまざまに移し替えられてゆく中で変わっていったのか、そしてその変わり方にはどのようなその時代その当時の世間一般その他おおぜいのわれわれの想いが、想像力が裏打ちされていたのか、といったことを考えてみたい、そんな思惑からかつて若い頃、まだいたいけな学者のふりをしていた時期に、それなりにマジメに取り組んだ仕事ではありました。
初版は1995年、もう28年前に毎日新聞社から出してもらいました。その後、2003年に文春文庫に入れてもらいましたが、残念ながらいまはどちらも在庫切れ、実質絶版になっています。それなりの図書館になら、まあ、入っている可能性はありますし、古本市場でも割と安く出回ってはいるようですので、ご興味あるようならばどうぞ探してみてください。

おはなしとしての無法松の一生というのは、ある時期までのニッポンの男らしさ、父親像みたいなものの典型として受け取られてきたところがありました。おはなしの主人公としては、武骨で不器用で無学で乱暴な明治時代の人力車夫ですが、それが当時の軍人の家庭と縁あってつきあうことになり、未亡人となったその軍人の奥さんと忘れ形見のひとり息子を、父親代わりとして見守り続けるというのが大きな筋立てになっていて、それを下地にしながら、その未亡人へのひそかな想いを抱くのだけれども、最後までちゃんと言い出せないまま、大きくなってゆくその息子にも疎まれるようになり、ひとり孤独のうちに死んで行く。でも、最後の死の床、木賃宿の布団の下に未亡人と息子名義の郵便貯金通帳が残されていた、というのがオチになっています。
武骨で不器用で無学で乱暴なオトコが、でも自分のその未亡人への想いを打ち明けることもできず、父親代わりに面倒をみてきたその息子にも疎まれ、献身は報われず終る――考えたらひどい話なんですが、でも、なぜかそのひどい話が「オトコらしさ」のあらわれの典型であり、また「純愛」だの「悲恋」だのといった装いでも増幅され、戦後ある時期まではほんとうに定番の「いいはなし」的に受け取られ、映画や芝居、歌謡曲その他にさまざまに移し替えられ、広まっていたおはなしではありました。
もともとは小説でした。「富島松五郎伝」というタイトルで昭和14年に、雑誌「九州文学」に発表されました。作者は岩下俊作。明治39年生まれで、1980年昭和55年に73歳で亡くなっています。この「九州文学」からはその少し前、昭和12年に火野葦平が「糞尿譚」で芥川賞を受賞していました。当時、大陸に出征中の陸軍伍長だった火野葦平はその後、徐州などの戦いに従事した体験や見聞をもとに「麦と兵隊」を書き、以後続編の「土と兵隊」「花と兵隊」など、実体験に取材した「兵隊もの」の大ベストセラー作家になってゆきます。そんな中、同じ文学仲間で親友だった岩下俊作も、芥川賞めざして小説を書いていた、そのひとつが「富島松五郎伝」でした。それが芥川賞でなく直木賞の候補になった。でも次点で落選するのですが、たまたまそれを眼にした当時の東京のインテリたちの一部に高く評価され、ひょんなことから伊丹万作の手にわたって、映画のシナリオに仕立てられた、それが「無法松の一生」というタイトルで昭和18年に公開された。「無法松」のおはなしとして世間に広く知られるようになるきっかけは、ざっとそんなものでした。
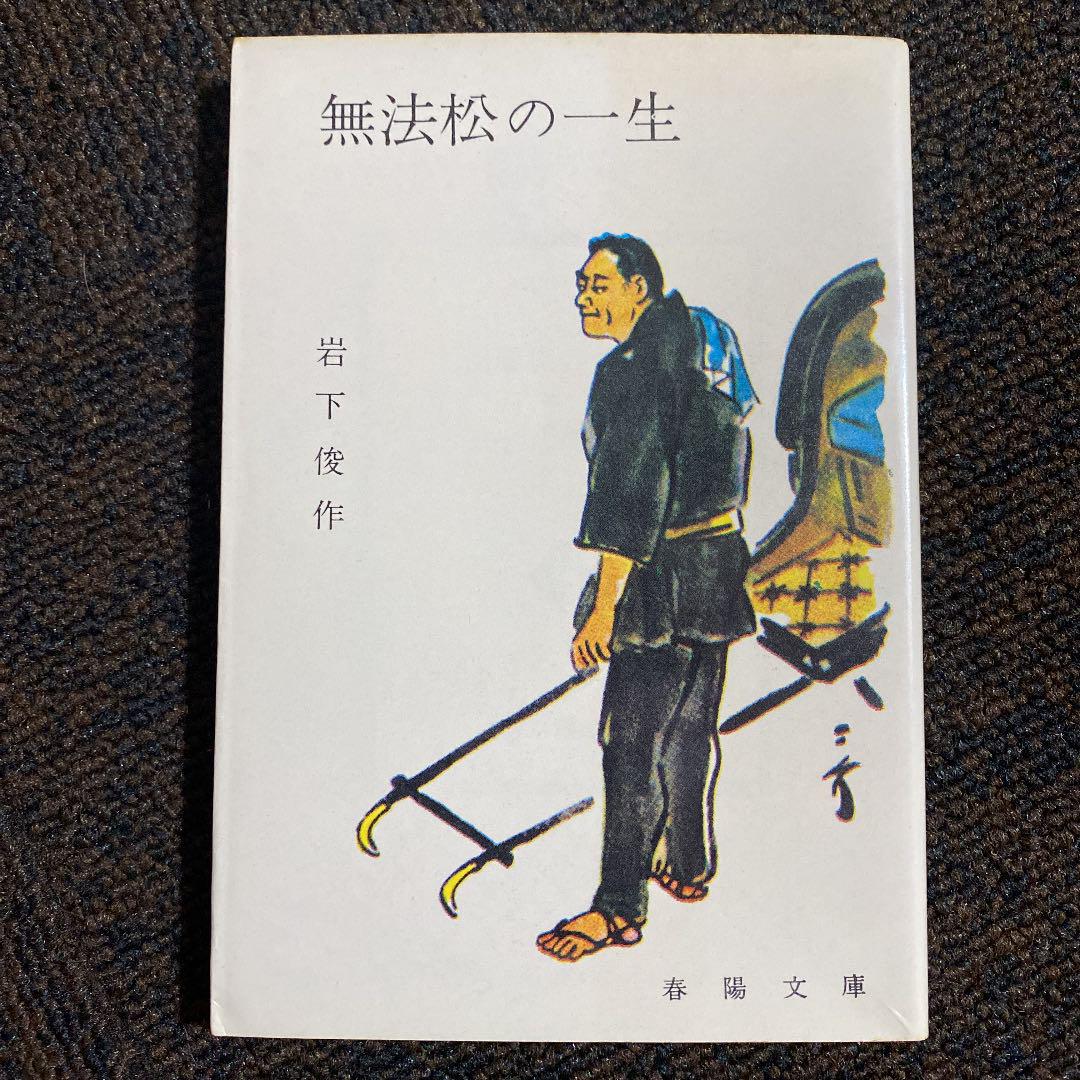
主演は坂東妻三郎。それまでの無声映画時代からチャンパラのスターだった人です。田村正和や田村正広ら田村三兄弟のお父さんだった人ですが、無声映画からトーキーに変わってゆく時代、彼が初めて肉声を映画に乗せた作品だったとも言われています。監督は稲垣浩。脚本の伊丹万作と共にこの作品に「惚れ込んだ」インテリのひとりで、これは戦後、何度も無法松をカバーすることにもなってゆきます。
ヒロインである未亡人、吉岡良子を演じたのが園井恵子という人で、これは当時の宝塚歌劇団出身の女優さん。映画のあと、全国を巡回慰問する劇団に参加していたところ、広島で原爆に被爆して他の劇団員ともども無惨な亡くなり方をした人ですが、そのことがまた、この無法松の一生の映画を戦後、伝説化してゆく大きなエンジンにもなりました。ある時期ある世代までの日本映画ファンの中に、この園井恵子演じる吉岡未亡人を青春のマドンナのように語る人たちは結構いたものです。今の女優さんだとのんさん、能年玲奈さんに顔つきなどは似た感じですが、貞淑な軍人の妻という、ある種理想の女性像として刷り込まれることになったようです。

未亡人となり母子家庭となった母と息子に、その外側から庇護者として、父親がわりを演じながら献身してゆく。その献身は息子に対してであると共に、しかし母親である未亡人にも向かってゆくという解釈は当然あり得るわけですが、でもそれを「恋愛」であり「果せぬ思い」を抱えたままの「純情」ゆえの「純愛」「悲恋」として解釈していったのは、もとの小説を読んで惚れ込んだり感動したりしてもちまわった当時の東京のインテリたちだったというあたりの、おはなしとしてのフィルターのかけられかたを、小説から映画、そして戦後にはさらに新劇の舞台やら歌謡曲やら何やら、さまざまなメディアに転生してゆく過程も含めて、まあ、跡づけてみながら、そこに投映されていたその時その時の「オトコらしさ」「父親らしさ」を透かしみようとした、といった次第でした。
このあたり、話し始めたらそれこそ大学の講義1年あるいはそれ以上かけてひとつずつ解きほぐさなければならない、われわれ日本人のこころのありように関する問いが山ほど出てくるわけですが、今日はそれらの中からひとつだけ、エピソードとしてご紹介しておきます。
この戦前、昭和18年の最初の映画版無法松でひとり息子を演じていたのは、のちの長門裕之でした。南田洋子の奥さんになり、若い頃はサザンの桑田佳祐そっくりの、でももっと向こう意気の強い戦後派若者を演じていた俳優でしたが、その彼が子役としてその息子をやっていた。「豚と軍艦」なんてよかったですねぇ。


一方、その母親である未亡人を演じる園井恵子は、宝塚の人で男役だったこともあり、それまで女性の役を演じたことがない、なのに無法松では明治の軍人の貞淑な妻をある種女性の理想像的にやらなければならなくなって悩むんですね。で、彼女が考えたのは、女そのものはよくわからないけれども、これはとりあえず母親をやればいいんだ、と理解することでした。なので、息子役の幼い長門裕之をやたら連れ回しては、猫っかわいがりしてみたそうです。それこそ膝に抱えたりなでたりとか、スキンシップもいっぱいしてたらしい。彼女としては一生懸命役作りをしていたんでしょうが、その時の体験をのちに、長門裕之自身は「ぼくのヰタセクスアリスは園井さんでした」と白状してるんですね。つまり、女というのはわからないけれども、女の理想型は母親だろう、ならばその母親というのはつまり子どもをかわいがるものだ、という当時の定型を懸命になぞろうとした結果、息子の長門さんはうっかり性的なものを感じてしまっていた、という、まあ、何とも皮肉なエピソードなわけです。このあたり、言葉本来の意味でのジェンダーとセクシュアリティと家族の関係の問題、およびその日本における歴史性なども含めて、いろんな問いが引き出せる挿話だと、いまでも思っています。

あるいは、無法松の一生の映画での呼び物シーンとして広く記憶されている、小学校の運動会に無法松が飛び入りして徒競走で優勝してしまうエピソードや、映画でもその後の無法松譚でも概ねクライマックスとされている、小倉の夏祭であった祇園太鼓に、これまた飛び入りで参加して、当時すでに忘れられていた古い太鼓の叩き方を披露するというシーン、これは作者岩下さんの創作で事実とは異なっているのですが、映画ではこれも無法松が表沙汰にできない苦しい思いを太鼓に込めて発散する、といった解釈に沿ってシークェンス化されていたりとか、まあ、ほんとにこの「無法松の一生」を叩き台にして、日本の近代のわれら日本人のものの見方や感じ方がどのようにおはなし化され、共有されていたのか、をときほぐしてゆく糸口がそこら中に埋め込まれているような印象すらありました。
というようなわけで、たまたまいま、札幌で上映中でもありますので、映画の無法松の一生、これは戦後、カラーで撮り直されたバージョンで、それをさらに4Kデジタルリマスターしたというふれこみの映像らしいですが、でも監督は戦前から同じ稲垣浩、脚本も伊丹万作のものに新劇が上演した際に、文学座の丸山薫が脚色を加えた、その後ほぼ「定番」となった無法松ですし、何より主演は全盛時の三船敏郎、吉岡夫人は高峰秀子でこれもまた、戦後的な無法松の配役としては共にキャラクターを戦前のものより戦後的に寄せたキャラになっているようにも思いますので、無法松の一生の想像力に刷り込まれていた原型、定型を知る意味では好適だと思います。
こういう解説になっています。
「明治三十年、初秋。九州・小倉の古船場に博奕で故郷を追われていた人力車夫の富島松五郎、人呼んで“無法松”(三船敏郎)が舞い戻ってきた。ある日、松五郎は木から落ちて足を痛めた少年・敏雄を助け、それが縁で敏雄の父・吉岡大尉(芥川比呂志)の家に招かれるようになる。酔えば機嫌よく唄う松五郎だが、大尉の妻・良子(高峰秀子)の前では照れくさくなり、声も出なかった。大尉が急死した後、松五郎は吉岡家の面倒を見るようになるが―。」
「戦時中の1943年(昭和18年)に公開され、大ヒットした阪東妻三郎主演『無法松の一生』から15年、稲垣浩監督が、人気絶頂の三船敏郎を主演にカラー、スコープサイズで自らリメイク。オリジナル版は検閲によっていくつかの場面がカットされてしまったが、このリメイクはヴェネツィア映画祭・金獅子賞を受賞。監督は無念を晴らした。」
しかし、 この無法松的男らしさ、父親らしさ、はその頼りになる存在という形象から、戦後の過程でどんどん零落してゆきます。戦後的価値観、民主主義的な言語空間があたりまえになってゆく中では、そのような無法松的な武骨で粗雑でといった男らしさは時代遅れのものになってゆき、ある意味嗤われる対象になってゆきます。このへん含めて、無法松の零落過程として、山田洋次の「馬鹿」シリーズなどから、それこそ初期の寅さん、男はつらいよなどに引き継がれてゆくというのが、自分の見立てで、そのあたりも折に触れて考察したりしてきていますが、それらはまた機会があれば改めて、ご紹介させていただければと思います。
ひとつ、ヒントとして言っておけば、それはわが国における信頼できる人間、リーダーシップを発揮するのは無法松的な「馬鹿」であること。それはあの森の石松などにも通じる、「馬鹿」という形象に対してわれわれ日本人がある時期まで確実に抱いていた信頼感、何か状況を変えてくれると思わせるような存在のひとつの定型にもつながっていたはずです。けれども、そのような「馬鹿」は戦後の過程で零落し、嗤われる存在になっていった。あの高倉健が「不器用な男ですから」というセリフと共に印象づけられていったのと同じ意味で、その「不器用」とはいまやセクシャルハラスメントの主体にもなりかねなくなっているあたりの経緯来歴など、改めて立ち止まってそれぞれのこころの内側にあったはずのそういう「馬鹿」のリーダーシップ、男らしさと紐付けられてもいたらしいそれらの形跡をたどりなおしてみることは、おそらく意味のあることだと想います。
高倉健、死ぬまでに無法松をやりたい、と言っていたらしいこと。そして山田洋次は全力でそれを停めていたという挿話などと共に、この無法松の一生、いまこのような時代、このような状況だからこそ、もう一度、とらえなおす機会になっていただければ、かつて無法松の影などという仕事をしていた自分としても、たいへんうれしいことであります。
今日のところは以上です。ありがとうございました。
*1:例によって、ch桜北海道の放映用、手控えor草稿として
