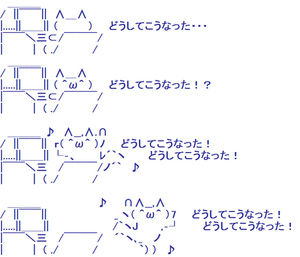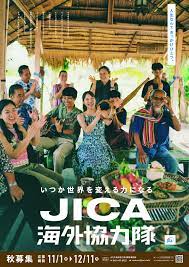昔話ね
— えいたろ (@eitarokougyou) 2025年11月3日
平成元年に70歳越えてた大工さんに聞いたこと
終戦直後大工の日当は500円
お弁当は蒸したさつま芋一本
その頃世田谷村の一坪が500円
オイルショックの頃日当8000円
手間請ってシステムがその頃出来て都会の建売大工が金持ちになった
日当2万円になったのがバブルの頃…
昔話ね
平成元年に70歳越えてた大工さんに聞いたこと
終戦直後大工の日当は500円
お弁当は蒸したさつま芋一本
その頃世田谷村の一坪が500円
オイルショックの頃日当8000円
手間請ってシステムがその頃出来て都会の建売大工が金持ちになった
日当2万円になったのがバブルの頃
そこから40年近く手間は上がってない
ここから劇的に日当が上がるとは思えない
僕がサイディング職人として手間請出来るようになったのが26歳で今から26年前
独立当時これ以上単価下がんないだろうと思ったらリーマンショック、東日本日本大震災までは単価が下がった
当時から常用手間はほとんど変わってない
材工で商売するようになって少し潤うようになりましたが
単価勝負は相変わらず
手間請メインの親方連中は外国人使ってる
この状況では職人さんの手間が上がることないと思うんですよね
この先ビックウェーブがあったとしても
最低限個人事業主として営業してないと乗り遅れてしまうと思う
バブルの時だって渡り歩くタイプの職人さんと社長さんは羽振り良かったけど
僕の師匠なんかは昔気質の棟梁だったんで今とそんなに変わらない手間でしたもの
自分の聞いた話しだと30年〜35年前くらいに千葉県で東急不動産の分譲やってた大工さんは手間請けで1日8万〜9万くらいになってたみたいッスよ!
バブルの恩恵を受けた人って感じですね😳
江戸川あたりの大工手間坪7万前後だったと聞いた記憶があります
ただ当時は墨付けて手で刻んでその値段だったんでそんなに良い金額ではないですね
サイディング職人も僕の親方世代は1日5万くらいになってたみたいで
1日3万にならないなら才能ないから辞めた方が良いってイヤミ言われて育ちました
お疲れ様です
空調ですがバブル期
1人工最高50000円でした。私達職人は馬鹿だから貯蓄する奴はほぼいなく、車はシーマ腕時計はロレックス毎週土日は高級焼肉や寿司屋で夕飯食べてました。
そのお金残ってれば
下職さんは凄かったですね
当時僕17歳で日当6000円で小僧としてボード張ってましたが
同じ歳のボード屋さんが月50万くらい取ってて
すごくスカウトされましたもん
現場朝礼が8時で帰宅は早くて20時〜22時で、まだ息子が2歳位で帰宅しても私の顔覚えて無く、どこのオッサンかと嫁に聞いてました。休みは月に一二回でしたよ
ボーナスは4回出ました。
うちの会社で少し前に引退した70過ぎの大工さんの話ではバブルの時は月100は余裕であったって言ってました。話盛ってたのかな
どこに住んでたかにもよりますね
関東で建売ブームに乗っかってガンガン叩いてた人は
100万くらい余裕で稼いでたと思います
僕がいたのは都内の工務店で手間請け大工さんが常備いるようなところじゃなかったので月50~60万くらいだったと記憶してます
僕は今サイディング屋ですが手間請け職人やってた頃で多い月で月70~80万稼いでました
一番多いときで締めの都合で120くらいでした
今は歳も取ったし単価が下がったのとやることが増えたせいで絶対無理ですね
建築の見積りで、一人一日5万とかでていても、実際にしはらわれるのは、2〜3万ってことですか?元請がピンハネしてる?
それをピンハネと表現してはダメだと思いますが
最下流の人間が受け取る金額はその通りです
だから僕たちは上を目指すんです
僕はサイディング屋なので建築のことは分かりませんが見積もりする際の設計労務金額は23000円前後です
それ以上だと相見積もりで勝てません
1人工50000円が常識になる日を夢見てます
都市部の大工で1000万越えとか沢山いたんよなー
その世代の大工は和室が作れて非規格品加工が可能な人達。もう殆どの人達が引退か鬼籍入りしている。現代の大工はハウスメーカーの規格品しか触れないのよ。ちょっとこの床上下を治してとかそういうのが無理。ただ部品を微調整して組むだけ。そこに移民が入るんだよ。日本人が爾後食えるわけ無いやん。
バブルはじけてから消費税が…
消費税を導入した、国政とそのその時の総理大臣…
安倍は2回消費税あげてます…
減税するべき時期に、増税してます…これが、今の日本をつくりあげた…
自分のメインで請負ってるHMさんでは常用単価ようやく18000、税別になりました。
ですので、その現場に手伝いで入ってもらう職人さんには自分もその金額を支払うつもりですが、別の職人さんはお互い大変だからと言って今まで通り15000支払う人もいます。