
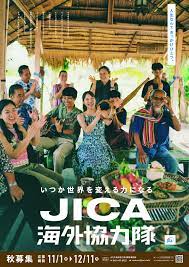
JICA大炎上になっていることをめぐって、ゆるく雑感。
JICAならJICAで、中で仕事している人がたの中には、猖獗極めているゆるふわキラキラwoke大正義な「空気」や「ノリ」に違和感抱いてる向きもいるのだろうと思う。
でも、それは、JICA本来の、そして今も大きな枠組みではそのために存在し、また実際に機能もしているであろう現実的な「国益」を求める組織、として日々仕事をしてゆく上での、いわば「必要なムダorコスト」的に眺めてうまくつきあっている、といった態度や認識もひとつあるのかもしれない、とは思う。
ある意味、〈おんな・こども〉の領域に対する少し前までの「昭和」「戦後」な「おとな≒オトコの成人≒社会的存在」の「そういうもの」としての態度なり認識なりと、系譜的には同じハコだったりする意味においても。
それは、何も今回のJICA案件に限ったことでもなく、たとえば、暇空茜氏の住民訴訟その他を介して、こちらがドン引きするほどミもフタもなくむくつけに露わになってしまったあのcolaboに対する都庁およびその上の厚労省界隈の現場のつきあい方、およそまともに「仕事」として、しかも「公共」の組織のそれとして接してきたとは思えないその態度や認識などにも、おそらく同じハコ的に通じるものとして。


例によって前々から言ってきていることのひとつではあるけれども、本邦のフェミニズムorフェミニストの言動や運動に対して当初そういう「おとな≒世間」の側が留保していた「そういうもの」としての〈おんな・こども〉的領域に対する態度や認識、などにも、それは間違いなく通底していたものでもあるはずで。
「多文化共生」「文化交流」「男女共同参画」「国際理解」……何でもいいが、いずれそれらの系のスローガンは、そういう意味で全部〈おんな・こども〉の領域として位置づけられていて、だから「そういうもの」として、多少ワヤでもスカスカでも、社会の実利の側に実際に利益をもたらすとは思えなくても、その具体的な成果やそこに至った経緯の検証など厳しくしなくてもいいものとして、「おとな≒世間」からは言わばお目こぼしされてきていたところがあったんだと思う。
その意味では、「趣味」や「道楽」みたいなものとして、具体的な「仕事」によってもたらされる「実利」――「儲け」「利益」といった世の中を支え、まわしている根幹の、その余剰なり余裕の部分でようやく存在できるものとして認識されているところがあったんだろう。そして、さらに敷衍するならそれは本邦人文社会系、いわゆる「文科系」の理屈や能書き、ガクモンについての「おとな≒世間」の態度や見方の「伝統」、要は「心の習慣」としての「そういうもの」としてあり続けていたものにも規定されているんだろう。
昨今、いわゆる「公金チューチュー」と揶揄されるようになっている公的な補助金や助成金の類をかっぱらうことに特化された今様レントシーカーの群れとその挙動についても、それを差配し分配する「公共」領域の側にそういう「心の習慣」が自明のものとして共有されていて、それが「公金チューチュー」しようと仕掛ける側と共鳴することで、いわば八百長的に企画が考えなしに通ってゆく構造になっているように見える。正気で考えるなら、どうしてこんな杜撰で穴だらけの企画書なり予算要求なりがそのまま通ってしまうんだろう、と訝るような事態がそこここで起こっているのは、何もそのようなお役所相手のペーパーワークだけでなく、いまどき本邦の社会的な組織や団体を動かしてゆく上での「文書」における「効率的」「合理的」な言葉やもの言い、文法や話法といったものが、ざっくりそのような「心の習慣」にあらかじめ同調する/できるようなたてつけになってしまっているかららしい。そしてそれは、同じく前々から拘ってきている大きなお題としての、あの「広告・宣伝」的なカネの流れに超伝導のごときなめらかさで同調してゆく言葉やもの言いの権力化の過程とも、間違いなく重なっている。「ゆるふわキラキラwoke大正義」な、本邦的DEI準拠のポリティカル・コレクトネスの現前のひとつのかたち。*1


本質的に「ムラはずれのキ●ガイ」衆でしかない「文科系」脳の、しかもそれに頼って世渡りしているような物件群は、そりゃ世の実利、経済や政治や法律その他のたてつけの絡み合いで動いている世の中の〈リアル〉の水準からは、そこに足つけている世間からも含めてそれこそ「疎外」されてきている。で、そんなキ●ガイ衆の能書きやリクツ、あるいは妄想空想お花畑の類を、ちょっとした珍奇なアクセサリーとしてであれ、あるいは本気で良きものとして信心しての上のことであれ、時にありがたがってくれていたのもある程度「そういうもの」だったのだけれども、*2 ただ、ある時期からそれを実利の〈リアル〉のたてつけにあらかじめ組み込んでしまい、実利で下支えされてまわっているこの社会まるごと、それら「ムラはずれのキ●ガイ」衆由来の理屈や能書きを「正しいもの」として、社会的に共有されるべき徳目にまでして儲けようとする動きが出てきたらしい。
世間一般その他おおぜいの側が、そういうキ●ガイ衆の「文科系」脳の発する理屈や能書きを広く「消費」する/できるような情報環境と言語空間が準備されていったこと。いわゆる大衆社会/消費社会化/情報社会化 (このへん何でもいい) のうっかりもたらしていったある現実。本邦に関してなら、直近地続きな間尺においては高度経済成長を契機に。*3
*1:おそらく関連。 king-biscuit.hatenablog.com king-biscuit.hatenablog.com king-biscuit.hatenablog.com king-biscuit.hatenablog.com king-biscuit.hatenablog.com king-biscuit.hatenadiary.com king-biscuit.hatenadiary.com king-biscuit.hatenadiary.com
*2:すでに1世紀以上も前、日本由来の美術品が西欧に注目されたことについての岩村透の戯作的な評言が、「美術」もまた、西欧社会においてもそのような〈おんな・こども〉の領域として〈それ以外〉の存在であったことに合焦している。「これ以前から日本の美術に注意するものが続々出て来、従って日本美術狂が現われてしきりに日本美術の妙を説き、また同時に美術品の蒐集家が出て来た。其の中には種々の人間があったろう。「サーここで一儲け」という奴もあったろうし、道楽でやった奴もあろうし、己れが物識りを誇る材料に使った者もあろう。慈善的に賞めた宣教師、外交的におだてた政治家、或いはバロン・メンハウゼン風に法螺一方に賞め吹いた連中もあったであろう。また己れが本国の美術界に不平の仇討の材料とした連中もあろうし、また中には実際心から感服して称賛した真面目の技芸家、批評家も大勢あったであろう。」
*3:このへん、一連ご参考。 king-biscuit.hatenablog.com king-biscuit.hatenablog.com king-biscuit.hatenablog.com king-biscuit.hatenablog.com king-biscuit.hatenablog.com